
|
図3.3.2.2−5 1989年10月の太陽フレア爆発前後のTECの変化
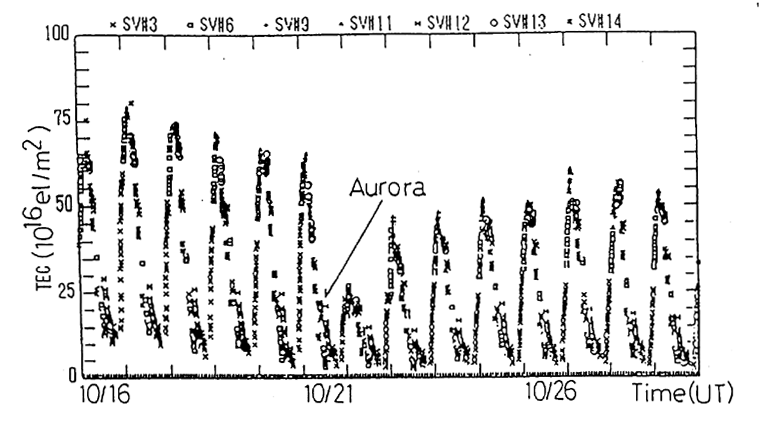
補正の効果は、基準局と利用者間の距離、電離層の状況により、一概に評価することは困難であるが、〔基準点(基準局)からの距離〕×2〜10PPM程度と考えられる。
このため、基線上が10?程度であれば、数?程度の誤差に収まると考えられるため、一般的な測位利用には十分であるといえる。
また、最近の動きとして、米国の提案で、信頼性の向上、電離層遅延補正を目的として、民生用第2チャネル(L5:L2の近傍の周波数?)の設地が検討されているが、実現するとしても、2000年頃打ち上げのBlock−?Rの途中からと考えられる。
3.3.2.3 GLONASSの現状
1. はじめに
GLONASSは1993年のロシア大統領令でシステムの推進が明らかにされてから順調な衛星打ち上げがあり、かねてよりの完成計画通り、1995年12月14日、軌道上に24個目の衛星が打ち上げられた。民生利用に関しては1995年3月、ロシア連邦政府から運用・方針が示されている。1995年末の24個の衛星によるシステム完成の発表の後1997年3月に到る間に新たな衛星の打ち上げはなく、その間に3個の衛星が利用できなくなっている。また短時間の不具合なども報告されており、システムの信頼性等の問題点が一部指摘されている。
一方、欧州のGNSS1をはじめとする航空用GNSSの完全性、性能向上および安定利用のための手段としてGLONASSは有力視されている。ロシアの積極的な姿勢を裏付けるものとして、1996年6月ロシア運輸省からICAOにたいして民間航空用に標準精度GLONASSを提供する申し出があり同7月ICA0が受理した経緯がある。1996年9月、米国のカンサスシティで開催されたlONGPS−96でもロシアのGLONASS関係者がはじめて出席し技術発表、討議が行われた。ここでは各国から10〜20のGLONASSに関する技術論文が発表された。さらにGLONASS情報に関し
前ページ 目次へ 次ページ
|

|